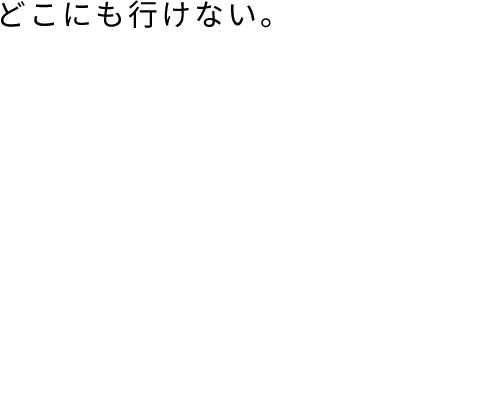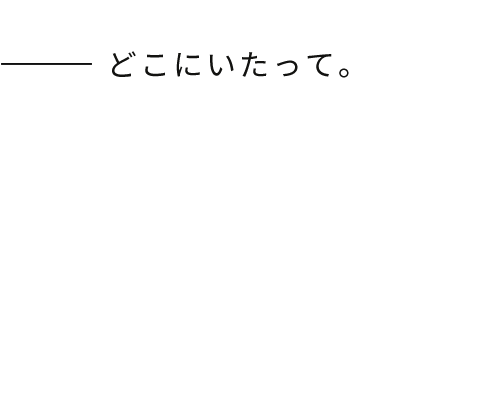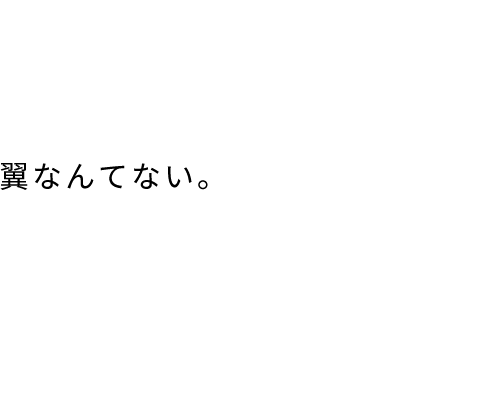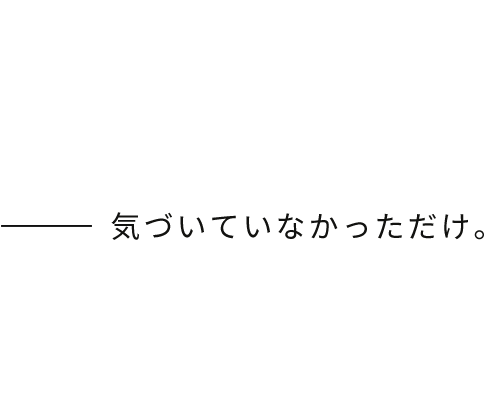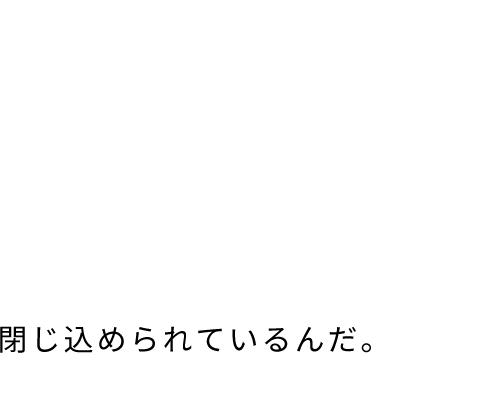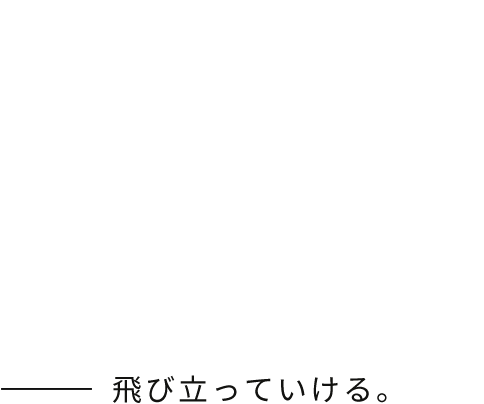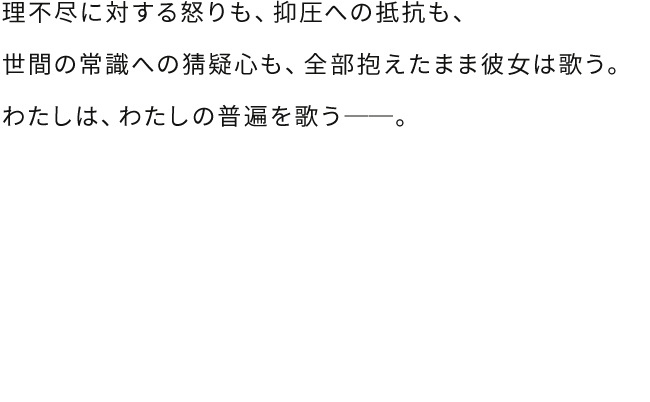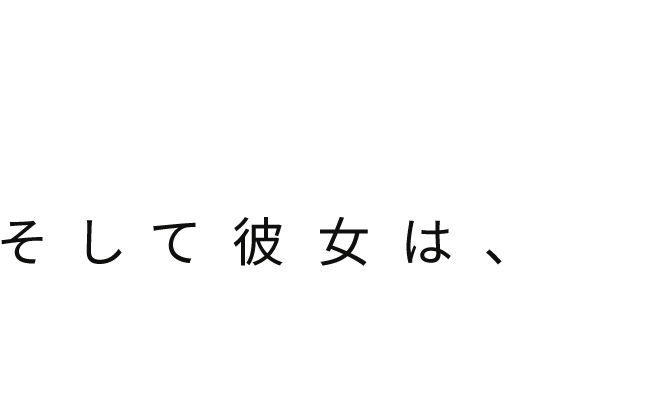-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
7

-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
-
1
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
『緊急事態宣言を発出することと致します』
なんで、どうして。
こんなにも何もかも、うまくいかないんだ。
抗いようもない状況に、彼女は立ち尽くすしかなかった。
街から人はいなくなり、不要不急なものはすべて、『自粛』を命じられる。
歌なんて、生きていくうえで必要不可欠〈エッセンシャル〉ではないと。
そう世界に宣告されたように、彼女は感じていた。
『帰ってらしゃい。もう、仕事も休みになったんでしょう?』
楽器や機材を揃えた、なんとか家賃を支払えるレベルの賃貸に、彼女は暮らしていた。
けれど、疫病禍は口に糊するための仕事を彼女から奪った。
「歌っていくこと」だけではない、「暮らしていくこと」すらも先が見えなくなってしまった。
やっと手に入れた、自分だけの場所。
疫病はそれを真っ黒に塗りつぶしてしまったかに思えた。
これからだと思っていた。
これから始まるんだと、思っていたのに。
……ダメだ。わたしはまだ、何もできてない
決めたはずだった。
歌い続けると。
あの閉ざされた町を飛び出して、自由な世界で。
歌って、歌って、歌って。
自分を否定したあの町に。あの人々に。
わたしはここに在ると、証明してみせると。
続けなきゃいけない。続けなくちゃ……届かない。
電話の向こうからは、母が心配そうに自分の名を呼ぶ声が聞こえる。
懐かしい声が彼女の耳の奥で甘く響いた。
だから……だから、わたしは……
けれど、それを母に告げることは出来なかった。 -
-
-
2
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
山々に囲まれた小さな町に、彼女は生まれた。
祖母は日本舞踊の師範。
2歳から中学生までの間、跡取りとして舞踊だけを徹底して教え込まれていた。
家の名に縛られて、他の生徒たちと比べても明らかに厳しく指導される。
舞踊から得たものは多かったかもしれないが、彼女にとっては呪縛でしかなかった。
強い抑圧の下で育っていた彼女は、いつも空想の世界で自らを癒していた。
鳥になり、翼を得て、空を自由に飛びまわる──
そして、彼女が出会ったのが、「歌」だった。
「わたし、あの先生キライー! 合唱なんて、フツーに歌ってればそれでいいじゃん」
小学校の授業、特に合唱で厳しかった音楽教師は同級生たちの間で嫌われていた。
けれど彼女だけは、違った。
それは、比べ物にならないほど厳しい舞踊の稽古を経験していたからかもしれない。
……面白い!
それは、最初は褒められたかっただけの理由かもしれない。
けれど、いつのまにか。
気づけば彼女は、いつも歌っていた。
舞踏の稽古の間で、一人の部屋で、通学途中で。
山道で、学校の廊下で、家のベランダで。
「ねえ……あなたって、いっつも歌ってるよね」
時には、友人といるときでさえも。
息をするように歌っていた。
歌っているときだけ、彼女の心は弾んだ。
決して友人がいなかったわけではない。
けれど、理解し合うことはひどく難しかった。
歌うことでしか、自分を守れなくなっていたのかもしれない。
もう嫌だ。わたしはもう踊らない。
高校生になった彼女は、ついに舞踊をやめることを決意した。
「あんたに何の才能があるっていうの? 日本舞踊しかないでしょう」
返ってきたのは呪詛の言葉そのものだった。
祖母のその言葉で、彼女は理解する。
求められていたのは舞踊の跡取りとしての自分。彼女自身を必要としてなどいなかったことに。
だから。
——見返してやる。やってやる。踊りじゃなくても、わたしは! -
-
-
3
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
彼女にとっての父は、理不尽な管理者だった。
進みたい道をことごとく否定され、一挙手一投足にまで監視の目が及んでいる。
それは「お前のため」という免罪符とともに押しつけられた歪んだ正義。
彼女はそう感じていた。
いつからか、父に心を開くことをやめた。
何を言っても無駄。どうせ否定されるだけだから。
だからこそ、早くこの家を、この町を出たかった。
この町のどこにも、居場所なんて出来なかった。
高校さえ出れば、わたしはこの町から出て行ける。
それだけが、彼女を生かしていた。
しかし──
それすらも、父は簡単に切って捨てた。
地元の大学へ、家から通うこと。
教員免許を取ること。
ほとんど命令のように父の口から放たれた言葉に、彼女は血が滲むほど唇を噛みしめた。
わたしが何をしたいか、なんて、この人は興味がないんだ──
それは無慈悲に告げられた懲役の延長。
わたしはこの家で、一生縛られて生きて行くしかないのか……?
歌も歌えず、父の思うとおりの人生を生きる?
二言目には「お前のためだ」とうそぶく父の作った檻の中で?
彼女の心の奥から、燃えるような怒りがわき上がった。
いやだ──!!
そんなの、死んでいるのと一緒じゃないか。
彼女は抵抗した。
せめて、自分の道が繋がるように、進学先の資料を漁り、勉学に精を出した。
この時ばかりは、父に何度も訴えた。
しかしと言うべきかやはりというべきか、父は彼女の言葉に耳を傾けることはなかった。
彼女は何度も、父の背中に襲いかかる夢を見た。
母がいなければ、それは現実にものになっていただろう。
「これが最後でいいから」
いつになく真剣に、母はそう言った。
その言葉が耳の奥で意味を結ぶまで、少しの時間がかかった。
──『最後』?
にわかに信じることは難しかった。
小学校を卒業したら、中学を卒業したら、高校を卒業したら──
そうやって期限を区切って我慢することで、どうにか生きてきた。
卒業したら、今より自由になれる。そんな希望を持っていた。
なのに、その希望が叶えられることはなかった。
『最後』という言葉の意味を彼女が問い返すと、母は微笑んだ。
「その後は、好きなようにしなね。自分の人生なんだから」
優しく、ぽんぽん、と背中をなでる母の手。
あくまで軽く、何の気なしに触れられた背中があたたかくなるのを感じた。
もしかしたら母は、祈りを込めてくれたのかもしれない。
背中から広がるぬくもりが、彼女の決意を固くした。
わたしはずっと、ずっと我慢してきた。だから……
この町に縛られるのは、これが最後だ。 -
-
-
4
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
大学を卒業し、彼女はようやく生まれ育った町を離れることができた。
驚いたのは、いざ家を出るとなった時、父が手を貸してくれたことだった。
引越の手配、機材のセッティング……あの家にいた時には見られなかった父の姿に、少しだけ戸惑った。
もしかしたら父は父なりに、彼女の決意を理解しようとしていたのかもしれない。
彼女の決意、それは──
ここで生きて行く。歌で生きて行く。
生きていく為には、まずは働くしかない。
初めから歌うことで生活できるなんて思うほど、彼女は甘く考えてはいなかった。
けれど。
生きていく為に必要な最低限のお金を稼ぐ為には、想像以上に時間を犠牲にしなくてはならなかった。
かと言って、音楽に費やす時間を削って働くのでは本末転倒だ。
必然、彼女は他の時間を削ることになる。
食べる時間。眠る時間。遊興にふける時間。
ただ外部からのインプットを完全に削ってしまっては、満足のいくアウトプットができるはずもない。
歌い続けるためには、望むような表現し続けるためにはどうしたらいいのか。
彼女は常に考えながら動いた。
「あなた、すごいわね! 頑張っているわね!」
時にそんな言葉をかけられることがあったが、彼女にはそんな実感はなかった。
頑張るとは、困難を越えるということだ。
彼女は歌うために必要な行動を、困難と感じたことは一度もなかった。
確かに、日々の生活も含めて簡単なことではない。
苦しくなかったといえば、嘘になる。
けれど、努力とは成功するまで続けなければ意味がないのだ。
やりたいことは見えている。
まっすぐに追いかけるだけだ。
その為に、ようやく手にいれた自由なのだ。
彼女は、生まれ育ったあの町にいた頃と比べたら、まるで翼を得て空を飛んでいるような心地よさを感じていた。
そうして、少しずつ手応えを感じ始める。
仕事にも慣れ、自由に使える時間も増えてきた。
都会での暮らしにも馴染み、以前の町ではありえなかった刺激的な出会いもあり、自分の音楽活動に必要な場所、道具、それらを手に入れる目星がついてきた。
ようやくここから自分の人生が始まる。
そんな時期だったのだ。
WHO、世界保健機関による正式名称はCOVID-19。
『新型コロナウイルス感染症』が、すべての世界を一変させた。
『緊急事態宣言を発出することと致します』
それはまさに、『平等な理不尽』だった。
人と会うことすら許されない。
経済は止まり、彼女も日用の糧を得る仕事まで奪われた。
──なんで……!!
我慢してきた。
ずっと我慢し続けてきた。
ようやく、ようやく自由を得て、自分の力で翼を得て、さあ飛び立とうとしていたその時だったのに!!
「ステイホーム。どうか皆様、今が我慢する時なのです」
そんなのはもうごめんなんだよっ!!!
もう諦めたくないんだ!!
いつまで、いつまで—— -
-
-
5
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
なんで、どうして。
こんなにも何もかも、うまくいかないんだ。
抗いようもない状況に、彼女は立ち尽くすしかなかった。
街から人はいなくなり、不要不急なものはすべて、『自粛』を命じられる。
歌なんて、生きていくうえで必要不可欠〈エッセンシャル〉ではないと。
そう世界に宣告されたように、彼女は感じていた。
『帰ってらしゃい。もう、仕事も休みになったんでしょう?』
楽器や機材を揃えた、なんとか家賃を支払えるレベルの賃貸に、彼女は暮らしていた。
けれど、疫病禍は口に糊するための仕事を彼女から奪った。
「歌っていくこと」だけではない、「暮らしていくこと」すらも先が見えなくなってしまった。
やっと手に入れた、自分だけの場所。
疫病はそれを真っ黒に塗りつぶしてしまったかに思えた。
これからだと思っていた。
これから始まるんだと、思っていたのに。
……ダメだ。わたしはまだ、何もできてない
決めたはずだった。
歌い続けると。
あの閉ざされた町を飛び出して、自由な世界で。
歌って、歌って、歌って。
自分を否定したあの町に。あの人々に。
わたしはここに在ると、証明してみせると。
続けなきゃいけない。続けなくちゃ……届かない。
電話の向こうからは、母が心配そうに自分の名を呼ぶ声が聞こえる。
懐かしい声が彼女の耳の奥で甘く響いた。
だから……だから、わたしは……
けれど、それを母に告げることは出来なかった。 -
-
-
6
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
帰ってこいと告げる母に向かって、スマートフォン越しに彼女は、
──笑ってみせた。
心配をかけたくなかった。
唯一「好きに生きろ」と言ってくれた母に、泣きつくことはしたくなかった。
本当は喉の奥まで出かかっていた。
──助けて。
その言葉を必死に飲み込んだ。
決めたはずなんだ。
歌い続けると。
歌って、歌って、歌って。
わたしはここに在ると、証明してみせると。
続けなきゃいけない。
続けなくちゃ……届かない。
彼女は言葉に詰まる。
もう、どうしたらいいのか分からなかった。
『……分かったわ。もうしばらく考えなさい』
今は何を言っても無駄と思ったのか、母親はため息とともに言った。
『そうよね。都会じゃなきゃ歌えないものね。こっちじゃできないものね』
その言葉は、ふわりと糸のように、彼女の心に絡みついた。
『じゃあ、また電話するわね。ちゃんと家にいて、外出する時はマスクをするのよ』
そう言って電話は切れた。
けれど彼女は、スマートフォンから手を放すことはしない。
──都会じゃなきゃ歌えない……
母の言葉を反芻しながら、手にしている文明の利器、その画面をタップする。
ここから繋がっているのは、世界。
開かれたアプリには、世界中から投稿された動画のサムネイルが並んでいた。
彼女が観ていた動画の履歴から、リコメンドされている動画たちだ。
それは当然、数多くのアーティストたちが世に送り出してきた音楽たち。
都会でなければ歌えない。──本当に?
心に絡みついた細い細い糸を、彼女は大切に大切に、手繰り寄せた。 -
-
-
7
7-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
懐かしい、草木が湿ったような香りが彼女の鼻をくすぐった。
疫病禍はテクノロジーを大きく発達させ、コミュニケーションの方法は実に多様化した。
手にした小さな光る板一つだけでも、世界中の誰とでも繋がれることができる。
彼女は細い糸を手繰るように、生まれた町へと戻った。
そして、その糸で新たな翼を編み上げる。
この町を囲む山々は高く、ともすれば閉じ込められているように感じるかもしれない。
けれど彼女は、すでに翼を手にしていた。
あとは空へと、大きく羽ばたけばいいのだ。
そして彼女は、もう一人ではなかった。
数多くの音楽を志す者たちがシノギを削るこの世界で、共に表現を高めあう仲間も手に入れていたのだ。
本音で語り合うことのできる、自分の歌を乗せる神のごとき旋律を紡ぎ出してくれる仲間。それを映像によっても観客へと訴求する力を持った仲間。
それは彼女が欲して止まなかった、不器用な自分と外の世界を繋いでくれる存在だ。 -